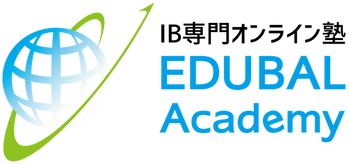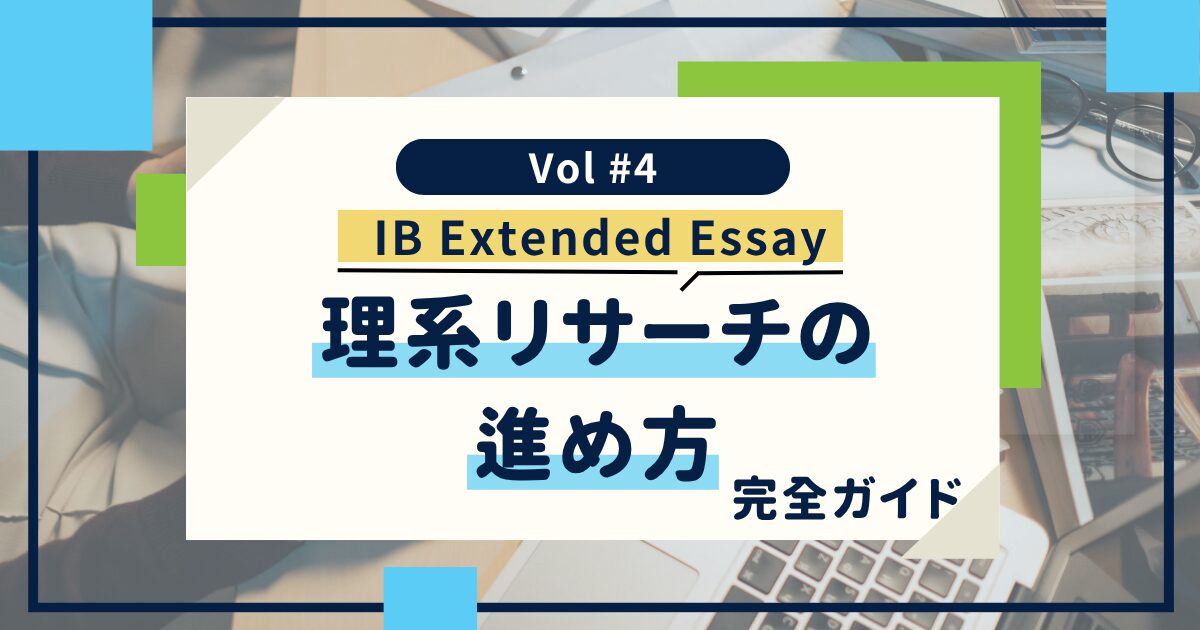EEに取り組み始めて、文献調査もほとんど終わったあなたを待つのは、とうとう自分のデータを集める「実験」のステップです。(文献調査についてはこちらの記事を参照)
EEの実験と聞くと、大学レベルの研究なんて無理、失敗したらどうしようなどと不安に思うかもしれません。
でも大丈夫!理系EEは、実は完璧な結果よりも、論理的ですきのない計画が評価されるんです。そこで、今回は、IBDPの先輩の例を用いながら詳しくステップについて紹介していきます。このステップに従って、計画を立ててみましょう!
Extended Essayって何?どのように評価されるの?
Extended Essay(EE)は簡単に言うと、IBの卒業論文にあたります。IBのディプロマ・プログラム(IBDP)のコア要素(TOK、CAS、EE)の一つで、英語で4000語(日本語の場合は8000字)の研究論文です。内容も形式もアカデミックな基準が求められ、大学レベルのリサーチペーパーの入門とも言えます。
どうやって評価されるの?
EEは、下のような観点で評価されます。
- 知識と理解:トピックや用語、研究手法をどれだけ理解しているか
- 応用と分析:どんな研究手法で、どんな分析をしているか
- 統合と評価:議論の展開や結論の説得力、研究の振り返り
- 構成と誠実性:論文の構成や引用などの学術的なルールが守られているか
EEとTOKの成績の組み合わせによって、最大3点がIBディプロマのスコアに加算されます。
Group 4(理系科目)のEEとは?
理系科目(Biology、Chemistry、 Physicsなど)でのEEでは、研究のすべての段階を科学的手法に基づいて進めることが求められます。この科学的手法とは、次の3つのステップで構成されます。
- 仮説を立てる
- 実験や調査でデータを得る
- 分析し、研究課題に答える
つまり、単に既存の研究を調べてまとめるだけではなく、自分自身でデータを集め、科学的根拠に基づいて結論を導くことが重視され、評価ポイントになります。
実験設計の7つのステップ
実験を行う場合、「なんとなくやってみる」ではなく、入念な計画を立てることが不可欠です。データの信頼性や実験の再現性、安全性までを考慮して初めて「学術的な実験」と言えます。以下のステップを踏むことで、評価基準に沿った実験を計画し、進めることができます。
1. 研究課題(Research Question)を決める
研究課題(Research Question)は実験の出発点です。問いが曖昧だと、仮説や方法がぶれてしまい、最後に「何を証明したのか」が分からなくなってしまいます。良い課題は「変数が明確」で、「答えを研究で示せるもの」です。(研究課題の選び方についてはこちらの記事を参照)
2. 仮説(Hypothesis)を立てる
仮説は、文献調査を踏まえて「自分なりの予想」を論理的に示す部分です。ただの直感ではなく、「過去の研究でこう示されている → 今回の条件ではこうなると考えられる」という形で、根拠をもって書きます。仮説があることで、得られた結果を「予想通りか/そうでなかったか」で明確に評価できます。予想が外れても失敗ではなく、むしろ「予想と違った理由」を考察することで論文の深みが出ます。
3. 変数(Variables)を整理する
三つの種類の変数をしっかり確認しましょう。
- 独立変数(Independent variable):自分が意図的に変える条件
- 従属変数(Dependent variable):結果として測定されるもの
- 制御変数(Controlled variable):外的要因を揃えることで、測定した結果が独立変数だけの影響であると確かめるもの
独立変数と従属変数は研究課題に対応している必要があります。また、IBの評価者は特に制御変数を大事にしています。制御変数の整理が曖昧だと、「測定した結果は本当にその変数の影響なのか?」と評価者に疑問を持たれてしまいます。制御変数は多ければ多いほど実験の信頼性が増すため、温度、時間、試薬の濃度、使用する機器の種類など、細かい条件まで丁寧に管理し、記述しましょう。さらに、制御変数を設定する理由や、もし管理できなかった場合に結果がどのように影響されるかを記述すると、論理的な説明として伝わりやすくなります。
4. 方法(Method)を設計する
方法設計では「理想」と「現実」のバランスが重要です。論文やプロの研究方法をそのまま真似するのは難しいため、自分の学校や家庭で入手可能な設備・材料に落とし込む工夫が必要です。また、方法の記述は、他人が読んで「再現できる」レベルで詳細に書きましょう。材料選びの理由や、測定方法の根拠を明記すると、評価が高くなります。
5. データの収集計画を立てる
「どのくらいのデータを、どの範囲・刻みで取るか」を決めるのは、実験設計の重要なポイントです。独立変数(Independent variable)の設定間隔を適切にすることで、変化の傾向をより正確に捉えることができます。また、繰り返し回数(Trial number)やサンプル数(Sample number)はデータや結論の説得力に直結しますが、単に多ければ良いというものではありません。時間やリソースとのバランスを取りながら、信頼性を確保できる適切な数を考えることが重要です。実験前に予備実験を行い、条件が適切か、測定がうまくいくかを確認することがおすすめです。
6. リスクを確認する
実験に伴うリスクは、安全面と倫理面の両方があります。
- 安全面:化学薬品の取り扱い、火器の使用、機械操作など
- 倫理面:動物や人を扱う場合の配慮、廃棄物処理の方法
リスクに言及しているかどうかは、実はEE評価でも重要なチェックポイントです。小さなリスクでも書いておくことで、実験に対する意識の高さを示すことができます。
7. スケジュールを立てる
多くの場合EEの実験に使える時間は限られており、短期間で多くの作業をこなす必要があります。そのため、時間配分を誤ると計画通りに進められなくなることが多いです。実験には予想外の失敗がつきものなので、やり直しが可能な余裕を持った計画を立てましょう。実験と同時進行でデータ整理や分析メモを進めておくと、最終執筆時に大きな助けになります。
Biologyで実験を行った先輩の例
例として、先輩が行った「プラスチック分解」に関連するEEの実験設計を紹介します。どのレベルの綿密な計画が求められるのかを知ることで、自分の実験設計をブラッシュアップするヒントになるはずです。
研究課題
「UV光の強度(0〜260 lux)がポリウレタンのリパーゼによる生分解速度にどのような影響を与えるか」
→ 研究課題は「独立変数(UV光の強度)」と「従属変数(生分解速度)」が明確に設定されています。
仮説
UV光を強く照射するとポリウレタンが光酸化で弱まり、リパーゼによる分解速度が上がる。
→ 仮説は先行研究を参考にしつつ、変数に対応する形で「なぜそうなるか」のメカニズムが論理的に書かれています。予想がデータと一致しなくても、考察で「なぜ違ったのか」を議論できる構造になっています。
変数の整理
- 独立変数:UV光の強度(0, 130, 160, 190, 260 lux)
- 従属変数:分解の進行度合い(600nmで測定した透過率の変化率)
- 制御変数:ポリウレタン濃度、粒子サイズ、酵素濃度、温度(25℃)、照射時間(2日)、使用装置や波長
→ 制御変数が細かく設定されている点が評価に直結します。温度や装置条件などを丁寧に管理することで、データの信頼性を担保できます。
方法と工夫の例
- UV強度の調整:透明フォルダーを重ねて光量を調整、センサーで正確に測定
- 測定方法:分光光度計で濁度を測定、透過率変化から分解速度を算出(先行研究で正当化済み)
- 材料調達:高価なCandida rugosaリパーゼの代わりに豚すい臓由来リパーゼを使用
- 前処理:酵素粉末のダマをコーヒーフィルターで除去し、ばらつきを軽減
→ 市販リパーゼへの代替、透明フォルダーによる光量調整、測定誤差を防ぐ前処理など、「限られた環境でも工夫して再現性を高める」姿勢が高く評価されます。
リスク管理
- 化学的リスク:リン酸緩衝液による刺激を避けるためゴーグルを着用
- 環境リスク:残渣をシンクに流さず危険廃液として処理
→ 安全性と環境配慮の両方に触れている点が良いです。IBの評価では、たとえ小さなリスクでも「事前に意識し、対策した」ことが重要視されます。
スケジュール
- 5回の実験日を確保し、最後の1回は失敗時のやり直しに充てる計画を立てました。最初の実験日では予備実験を2回行い、条件の妥当性を確認したうえで2日目から4日目の本実験に取り組んでいます。
→ 実験では思い通りに進まないことが当たり前なので、余裕を持った計画は欠かせません。また、予備実験も最初から予定に入れておくと、思いがけないミスを防止できます。
実験以外のアプローチ
理系EEというと「必ず実験をしなければならない」と思われがちですが、必ずしも自分で実験を行う必要はありません。実際、実験環境や時間に制約があるIB生にとって、以下のような方法も有効です。
- データベースの活用:WHO、NASA、Our World in Data など信頼性ある大規模データを自分の新しい切り口から分析する
- シミュレーション・モデル化:現実には試せない条件を再現し、理論の裏付けを得る
- 調査・アンケート:人間行動や環境意識を調べ、心理学や環境科学に応用する
また、こういったアプローチから複数の方法を組み合わせることで研究の厚みが増し、IBが重視する「批判的思考」も示せます。
まとめ
理系EEは「自分の手でデータを扱う」経験を得られる貴重な機会です。
実験に挑戦する場合も、データ解析やシミュレーションに頼る場合も、計画性と批判的思考がカギとなります。準備をしっかり行い、学術的に価値のある研究を目指しましょう。
計画的で効率的なEE対策にはEDUBAL Academy
EDUBAL Academyでは、Extended Essayの指導に加えて、IBの最終試験の元採点官と教員が監修したカリキュラムを用いたIB科目の学習サポートや、大学出願に向けたアドバイザーによる学習計画・進学支援も行っています。
「EEの進め方がわからない」「今のペースで間に合うのか相談したい」―そんなIB生の悩みに教師とアドバイザーが寄り添い、フルサポートします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください!
▶ 無料相談はこちらから:お問い合わせ・無料相談