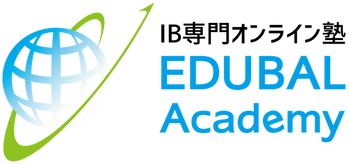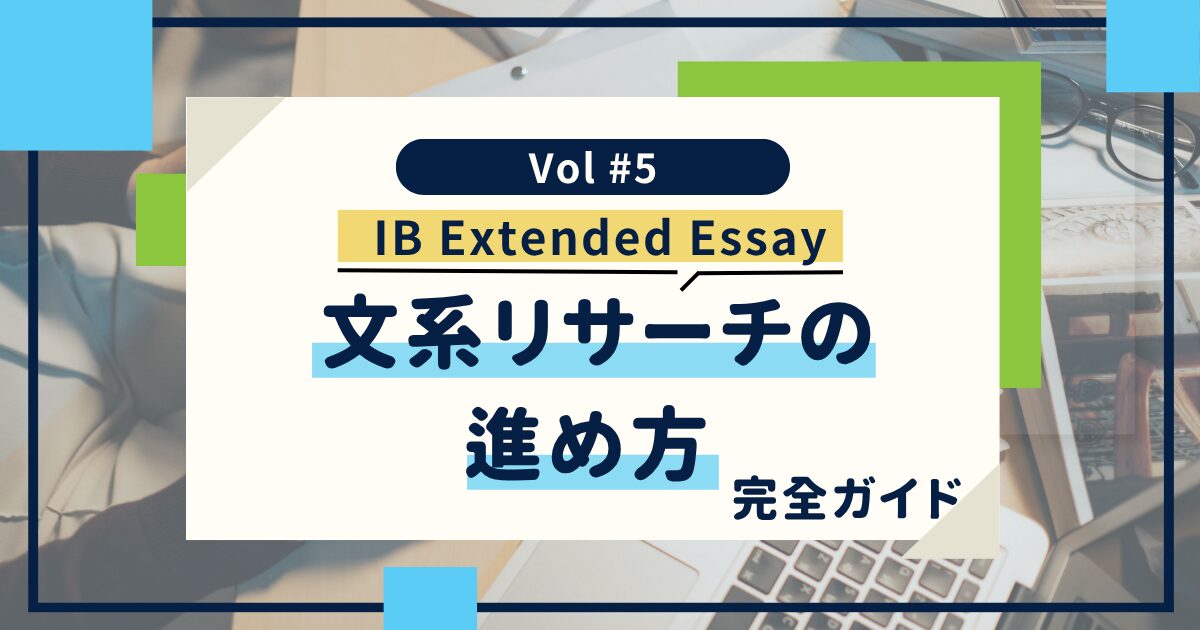EEに取り組み始めて、文献調査もほとんど終わったあなたを待つのは、いよいよ「自分のリサーチを組み立てる」ステップです。(文献調査についてはこちらの記事を参照)
「実験がないなら何をすればいいの?」「どうやって自分の研究にオリジナリティを出すの?」と不安に感じる人も多いでしょう。
でも大丈夫!文系EEでは完璧な結果よりも、自分のオリジナリティーを持った論理的で一貫したリサーチプロセスが評価されます。
今回は、IBDPの先輩の具体例を交えながら、文系EEのリサーチの進め方を1から10まで分かりやすく紹介します。
Extended Essayって何?どのように評価されるの?
Extended Essay(EE)は簡単に言うと、IBの卒業論文にあたります。IBのディプロマ・プログラム(IBDP)のコア要素(TOK、CAS、EE)の一つで、英語で4000語(日本語の場合は8000字)の研究論文です。内容も形式もアカデミックな基準が求められ、大学レベルのリサーチペーパーの入門とも言えます。
どうやって評価されるの?
EEは、下のような観点で評価されます。
- 知識と理解:トピックや用語、研究手法をどれだけ理解しているか
- 応用と分析:どんな研究手法で、どんな分析をしているか
- 統合と評価:議論の展開や結論の説得力、研究の振り返り
- 構成と誠実性:論文の構成や引用などの学術的なルールが守られているか
EEとTOKの成績の組み合わせによって、最大3点がIBディプロマのスコアに加算されます。
Group 1/2/3(文系科目)のEEとは?どんな研究手法があるの?
文系科目(History、Economics、Psychology、Global Politics、Language and Literatureなど)のEEでは、理系EEの「実験」にあたる部分を「調査・分析」で行うのが特徴です。理系EEよりも多様な研究手法があり、研究目的に応じて適切な方法を選ぶことが成功の鍵です。
主な研究手法の例
- 一次資料分析(Primary source analysis):文学作品、歴史文書、ニュース記事、スピーチなどの一次資料を詳しく読み解く。
- データ分析(Data analysis):経済データや世論調査などの統計をもとに、仮説を検証する。
- インタビュー・アンケート(Interviews / Surveys)分析:当事者や専門家、一般の人々の意見を自分で直接集め、データとして分析する。
このように、理系EEのような「実験室での観察」はなくても、自分の立てた問いに対して、自分で選んだ方法で結論を導く姿勢が評価されます。
単なる知識の整理や理論の紹介で終わらせず、「なぜこのテーマを選び、どのように分析したのか」という研究者としての視点が大切です。
リサーチ設計のステップ別ガイド
1. 研究課題(Research Question)を決める
研究課題(Research Question)は実験の出発点です。問いが曖昧だと、仮説や方法がぶれてしまい、最後に「何を証明したのか」が分からなくなってしまいます。良い研究課題は、「データ・文献をもとに検証できる」、「範囲が広すぎず、4000語で答えられる」という特徴があります。(研究課題の選び方についてはこちらの記事を参照)
2. 資料を整理する
「どんなデータ・資料を分析対象にするか」を明確にしましょう。資料には大きく2種類あります。
- 一次資料(Primary source):自分で集めたデータ(インタビュー、アンケート、観察、フィールドワークなど)や当時の記録・情報。
- 二次資料(Secondary source):既に発表されている論文、報告書、書籍、新聞記事、統計データなど。
一次資料は独自性とリアリティがありますが、収集に時間がかかり、偏りが生じる可能性があります。 一方、二次資料は信頼性が高く、理論的背景を整理するのに役立ちますが、他者の分析をなぞるだけでは新規性が弱くなります。
文系EEでは二つの種類の区別が曖昧になりがちですが、それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、研究目的に応じて組み合わせることが大切です。文献調査で二次資料を押さえたうえで、一次資料を組み合わせると、研究に独自性と深みが生まれます。
3. 一次資料をどのように集めるか(Primary research)を決める
Primary data(一次資料)をどのように集めるかを計画します。一次資料を集めるPrimary researchの必要性に関しては先輩もこのように語っています:
Primary Researchを行わない手はないと思います。自分で集めたデータがあると、EE全体の骨格がしっかりします。時間はかかりますが、早めに始めれば大きな武器になります。
2023年卒・Geography EEを執筆
研究テーマに関する背景をよく理解した上で、「誰に」、「なぜ」、「どんな情報を得るために」その方法を使うのかを明確にしましょう。代表的な方法には以下の方法があります:
- インタビュー:少人数を深く掘り下げ、背景や意見を質的に分析。
- アンケート:多くの人から広く意見を集め、傾向を定量的に分析。
- 文献・資料収集:特定の時期や主題の写真、資料を体系的に集めて分析。
4. データ収集の方法を設計する
インタビューやアンケートを実施する場合、調査対象、人数、質問内容、実施方法を具体的に決めます。
【質問設計】
- 定量的(Quantitative)質問:選択肢やスケールで答える形式。数値分析に使いやすい。
- 定性的(Qualitative)質問:自由記述形式で意見や背景を深く探る。
両方を組み合わせると、データの幅と分析の深さが増します。先輩も分析についてこのように語っています:
SurveyやInterviewなど、主観的な評価もスコア化して比較すると、定性的な研究でも説得力が増します。
2023年卒・Geography EEを執筆
【サンプル設計】
- 小規模調査なら全員調査(Census)
- 大規模調査ならサンプル調査(Sample)
- 偏りを避けるため、できるだけランダムに対象を選ぶ
調査対象の数は多ければいいのではなく、研究目的に対して適切で現実的な数を設定しましょう。
【倫理的配慮と信頼性の確保】
- 対象者の同意を得る(インフォームド・コンセント)
- 匿名性を守る
- 誤解を招く質問を避ける
- 公共の場での調査は必要に応じて届け出を出す
5. 分析方法(Methodology)を選定する
集めた一次資料と二次資料をどう組み合わせて分析するかを明確にします。
- 定量的分析(Quantitative):統計やグラフを用いて傾向・関連を数値的に説明(例:価格変化、投票率の推移など)
- 定性的分析(Qualitative):インタビュー内容やテキストを分析し、意味・背景・文脈を読み解く(例:政策論調やメディア表現の比較など)
分析方法は、研究課題との整合性が最も重視されます。データをどのように扱い、どんな視点から解釈するのかを明確にしておくことが重要です。
められなくなることが多いです。実験には予想外の失敗がつきものなので、やり直しが可能な余裕を持った計画を立てましょう。実験と同時進行でデータ整理や分析メモを進めておくと、最終執筆時に大きな助けになります。
まとめ
文系EEは、「どんなデータをどのように扱い、何を根拠にして結論を導くか」が問われる研究です。
扱う資料が Primary data(一次資料) でも Secondary data(二次資料) でも、重要なのは、明確な根拠を用いて論理的にリサーチクエスチョンに答えることです。
興味のあるテーマを深く掘り下げ、自分の視点で世界を分析することがEEの醍醐味です。
このリサーチ経験は、大学以降の学術的思考力や探究的な姿勢の基礎となり、今後の学びやキャリアに必ず活きてくることでしょう。
このブログでは、テーマ設定・リサーチ・構成・執筆など、Extended Essayの書き方をシリーズで詳しく紹介しています。次は、「実際の執筆作業について知りたい」という方も、ぜひまたチェックしてみてください!
計画的で効率的なEE対策にはEDUBAL Academy
EDUBAL Academyでは、Extended Essayの指導に加えて、IBの最終試験の元採点官と教員が監修したカリキュラムを用いたIB科目の学習サポートや、大学出願に向けたアドバイザーによる学習計画・進学支援も行っています。
「EEの進め方がわからない」「今のペースで間に合うのか相談したい」―そんなIB生の悩みに教師とアドバイザーが寄り添い、フルサポートします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください!
▶ 無料相談はこちらから:お問い合わせ・無料相談