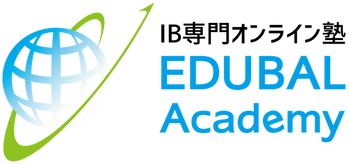こんにちは。
IB生専門のオンライン個別塾「EDUBAL Academy」です。
国際バカロレア(IB)を修了した生徒は、世界中の大学に出願する資格を持っています。つまり、進路の選択肢は非常に幅広いのです。
一方で、選択肢が多いからこそ「自分に合う大学はどこか」「併願はどう組むべきか」と悩むIB生も少なくありません。
そこでこの記事では、国内外の入試制度の基本情報を整理し、IB生が進路選びを始める際に押さえておきたいポイントをご紹介します!
IB生が出願できる国内外の大学入試制度の全体像
IB生が利用できる主な入試制度を、国内と海外に分けて見てみましょう!
日本国内でIB生が受験できる主な入試制度
日本の大学では、IBDP取得者を対象とした入試制度が広く整備されており、IB入試をはじめ、総合型選抜(AO入試)や帰国生入試、学校推薦型入試などで出願が可能です。いずれも大学ごとに要件は異なりますが、IBスコアに加え、小論文・面接・書類審査を組み合わせた総合評価が行われるのが一般的で、学業成績だけでなく課外活動や資格も重視される点が特徴です。
| IB入試 | ⚫︎ IBDP取得者のみが対象で、一部の大学で実施されている。 ⚫︎ 共通テストが免除されることが多く、IB生にとって受験しやすい制度。 ⚫︎ 志願者は5〜20名程度と少なく、IB生の中で合格者が決定する。 |
| 総合型選抜 (AO入試) | ⚫︎ 各大学のアドミッションポリシーや、求める人物像と合致する志願者を評価するため、書類審査・筆記試験・面接を課せられる場合が多い。 ⚫︎ IBDPを取得していなくても受験でき、国内外の幅広い生徒が対象のためIB入試よりは倍率が高い可能性がある。 ⚫︎ 日本語学位は4月入学、英語学位は9月入学が一般的。 |
| 帰国生入試 | ⚫︎ 一般的に継続して2年以上海外在住経験がある生徒が対象で、IBスコアを活用できる場合もある。 ⚫︎ IBスコアを使う場合、海外でIBDPを取得していることが条件であることが多い(一部の大学は日本のIB校でもOK)。 ⚫︎ AO入試と同様にIBDPを取得していなくても受験可能だが、倍率はIB入試より高い可能性がある。 |
| 学校推薦型選抜 | ⚫︎ 公募推薦と指定校推薦の2種類に分けられる。 ⚫︎ 公募推薦はどの高校からでも校長推薦があれば出願可能、指定校推薦は指定校のみ。 ⚫︎ 推薦状が必須で、大学によっては共通テストの受験が求められる場合もある。 ⚫︎ 学業成績や人物評価が重視され、評定平均が基準を満たす必要があることが多い。 |
まず、IB入試はIBDP取得者のみを対象とし、国内では一部の大学で実施されています。この入試ではIBスコアを重視し、共通テストが免除される場合が多いため、IB生にとって受験しやすいのが特徴です。また、募集人数は大学のプログラムによりますが、5〜20名程度と少ない傾向があります。大学によってはIB入試の他に、AO入試(総合型選抜)として受験できる場合があります。
次に、AO入試(総合型選抜)は国内外の生徒が対象で、IBスコア以外の提出で出願ができるため、倍率はIB入試より高い傾向があります。選考では、課外活動記録、志望理由書、推薦状などの提出書類に加えて、面接やプレゼンテーション、さらには筆記試験が課されることもあります。理系学部では、数学や理科の基礎的な知識を問う試験や口頭試問が実施されることもめずらしくありません。AO入試の大きな特徴は、学力試験だけでなく「総合的な人物評価」が重視される点。各大学のアドミッションポリシーや求める人物像に沿って、志願者の適性や意欲を多角的に評価されます。日本語学位の場合は4月入学が一般的で、英語学位では9月入学が多いです。
帰国生入試は海外での生活経験がある学生を対象とし、IBスコアを使用できる場合がありますが、IBDP取得は必須ではありません。そのため、AO入試と同じく倍率はIB入試より高い可能性があります。しかし、IBスコアを帰国生入試で使用する場合、一般的には海外の現地校やインターナショナルスクールでIBDPを修了している必要があります。選考は書類審査に加えて、面接や小論文が課されることが多く、理系では口頭試問や科目試験を含む場合もあります。
最後に、学校推薦型選抜という選択肢もあります。公募推薦と指定校推薦の2種類があり、公募推薦はどの高校からでも学校長の推薦があれば出願できます。一方、指定校推薦は大学が指定する高校に在籍している場合のみ出願可能です。一般的には、筆記試験、口頭試験、資格試験結果、基礎学力の確認、共通テストが加味されます。ただし、大学によっては共通テストの受験が必要な場合もあるため、事前に確認が必要です。
国内大学への出願時期は、IB入試・AO入試・帰国生入試いずれも7月または9月が中心です。IBスコアを活用できる大学には、早稲田大学(政治経済学部・国際教養学部・人間科学部)、慶應義塾大学(法学部・総合政策学部・環境情報学部・経済学部)をはじめ、上智大学、国際基督教大学(ICU)、立命館大学などがあります。また、AO入試や帰国生入試を採用している大学は幅広く、英語で学位取得が可能なプログラムや国際色豊かなカリキュラムを持つ学部で多く導入されています。
詳細な一覧はIBを活用した大学入学者選抜例(2024年3月6日時点)をご覧ください。
このように、日本国内にはIB生向けの多様な入試制度があり、出願の幅が広がっています。自分に合った制度を理解し、各大学の募集要項をしっかり確認しながら計画的に準備を進めることが重要です。また、IB入試と帰国生入試などの併願可否は大学によって異なるため、必ず各大学の募集要項を確認してください。
海外でIB生が受験できる主な入試制度
海外大学の入学者選抜では、IBスコア(予想スコア:Predicted または最終スコア:Final)が幅広く活用されています。例えば、イギリスの大学では、中央機関であるUCASがIBスコアや英国の共通試験であるAレベルなどのスコア換算表を作成し、各大学はこの換算を参考に条件付きの入学オファーを出しています。この「条件付き」という仕組みは、出願時点では最終スコアが確定していないため、IB予想スコアをもとに仮の合格を出し、最終的に必要なスコアを取得すれば正式合格となるためです。一方、アメリカの大学では、SATなどの共通試験や高校の成績(GPA)を総合的に評価する仕組みが一般的で、特に選抜制の高い大学では、IB履修を推奨したり、積極的に評価したりするケースが多く見られます。カナダや他の国の大学もIBスコアを評価する傾向が強く、条件付き合格を出すことが一般的です。
さらに、海外の多くの大学では、IBのHL科目で一定の得点を取得した学生に対して、入学後にその科目に相当する大学授業の履修免除や単位認定を行う制度があります。これにより、IB生は大学での履修負担を軽減できるメリットを受けることできます。ただし、この仕組みは大学や学部によって異なるため、出願前に確認しておきましょう。
国ごとの出願制度と特徴
アメリカの大学は、Common Application(共通出願システム)やUC System(カリフォルニア大学専用システム)を通して出願します。必要書類には、GPAとIB予想スコアもしくはSAT、ACTなどのオプショナルで成績を証明するもの、エッセイ、課外活動記録、推薦状、そしてTOEFLやIELTSなどの英語力証明が含まれます。近年は、SATやACTなどの標準テストを提出しなくても出願できる「テストオプショナル」制度を導入する大学が増えています。出願スケジュールは、Early Decision(早期専願)が11月、Regular Decision(通常出願)が1月であることが一般的です。また、MITやリベラルアーツカレッジなど、一部の大学は独自のポータルを使用しています。
イギリスの大学では、UCAS(Universities and Colleges Admissions Service)を通じて最大5校まで同時に出願可能です。全ての大学に共通のPersonal Statement(志望理由書)を提出する必要があり、審査はIB予想スコアや書類を中心に行われます。合格は条件付きで出されることが多く、最終的にはIBの最終スコアで入学可否が決定します。出願期限は、医学部やオックスブリッジ(オックスフォード大学・ケンブリッジ大学)が10月中旬、それ以外の学部は1月中旬となっています。
カナダの大学では、GPAやIB予想スコアを重視する点でイギリスやアメリカと似ていますが、出願は各州や大学独自のポータルを利用します。多くの場合、条件付き合格(最終試験で一定スコアを取れば入学許可)を出し、11月頃から出願が始まり、通常は2月頃が締め切りです。
このように、国ごとに出願制度や評価基準には違いがありますが、特にアメリカ、イギリス、カナダは日本のIB生に人気が高い進学先です。その他にも、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドなどもIB生に人気の留学先として挙げられます。
海外の大学では、IBスコアを評価して入学選抜に活用するケースが多く見られますが、奨学金制度の充実度は国や大学によって異なります。例えば、特にアメリカ、イギリス、カナダではIBスコアや学業成績を基にした奨学金が比較的充実しており、留学生にも広く門戸を開いています。特にこの3カ国では奨学金が存在するものの、競争率が非常に高く、特定の大学やプログラムに限られる場合が多いです。このため、奨学金を検討する場合は、国や大学ごとの条件を事前に詳しく調べることが重要です。
IB生が進路を選ぶ際の4つの視点
- 自分の価値観とマッチしているか
大学選びでは、出願条件だけでなく、自分の価値観やライフスタイルとの相性も重要です。
例えば、
- 海外生活に挑戦したいのか、
- 勉強中心の生活を送りたいのか、
- 学生コミュニティでの活動を重視したいのか、
- 英語や外国語を中心とした生活を送りたいのか、
- 日本語環境を維持したいのか、など
といった優先順位を明確にしておくことで、進路選びの迷いを減らすことができます。
- 学びたいことが学べる環境か
大学で自分が本当に学びたいことを学べるかどうかも重要です。
カリキュラムや授業スタイルを出願する事前に確認し、少人数で議論型の授業が多い大学では、ディスカッションやプレゼンの機会を通してIBの学び方と親和性が高い学習体験が得られます。
一方、講義中心型の大学では、授業中の発言が少なくても学習が進めやすく、受け身の学生でも学びやすいという特徴があります。
また、カリキュラムの方向性も確認しましょう。専門性重視型は一つの分野を深く学びたい人に向き、リベラルアーツ型は幅広く学び、興味の幅を探求したい人に向いています。
- 自分のIBスコアで出願できるか
IB生の場合、出願条件としてIBスコアの基準が明確に設定されていることが多いので、大学に出願する際は、まず自分のIBスコアが出願条件を満たしているかを確認することが重要です。国内大学では、IBスコアの点数に加え、課外活動の実績、面接、志望理由書なども総合的に評価されます。特に人気大学では、IBスコア35点前後が目安とされますが、30点前後でも面接や小論文で高い評価を得られれば合格の可能性があります。つまり、単純な成績だけでなく、自分の適性や熱意を示すことも重要です。
一方、海外大学では、IB予想スコア(Predicted)や最終スコア(Final)に基づいて条件付き合格(Conditional Offer)が出されることが一般的です。この場合、合格を得るには一定のIBスコアやHL科目の履修、必要に応じてエッセイや推薦状の提出が求められます。アメリカやイギリスなどでは、成績だけでなく、学問への意欲や将来の目標を示すエッセイや活動履歴が合否に大きく影響する場合もあります。スコアが高いほど合格のチャンスは広がりますが、大学やプログラムによって重視される要素は異なるため、出願先の選考方針をしっかり確認することが重要です。
- 将来どこで働きたいか、何をしたいか
進学先は、卒業後のキャリアにも影響します。海外の大学進学は現地就職やグローバルキャリアを目指す場合に魅力的で、日本に帰国した場合も日本語と外国語を活かした外資系企業やグローバル企業での就職に有利です。ただし、海外を拠点としながら日本の企業でオンラインインターンや企業との接点を持つ場合、時差や環境の違いによる制約や調整が必要になる点には注意が必要です。
一方で、国内大学に進学するメリットは、国内企業とのつながりやインターンの機会が豊富で、就職活動の情報やサポートを受けやすい環境が整っていることです。また、日本語での学びやキャンパス生活を維持できるため、言語面での不安が少なく、地元での就職や生活を見据えたキャリア形成がしやすいという利点もあります。さらに、国内大学でのネットワークや卒業生とのつながりは、新卒就職活動において大きなアドバンテージとなることも多いです。
まとめ
大学進路の選択肢は多くても、自分に「合う進路」は一つだけではありません。
IBはあくまでスタートラインなので、大切なのは、「何ができるようになったか」「どんな学び方が自分に合っているか」を理解したうえで進路を選ぶこと。
選択肢が多いからこそ、早めの情報収集と、自分なりの軸づくりが鍵になります。
このブログでは、今後も国内と海外の大学出願方法、出願や大学生活の体験談などをシリーズで詳しく紹介していく予定です。
「次はIBで進学できる国内大学の仕組みと選び方の基本が知りたい!」という方も、ぜひまたチェックしてみてください!
迷わないで大学進路を決めるならEDUBAL Academy
EDUBAL Academyでは、IBの指導に加え、大学受験に必要な最終試験を元採点官・教員監修のカリキュラムでサポートします。さらに、大学出願に向けたアドバイザーによる学習計画・進学支援も行っています。
- 志望大学に向けて学力を上げたい方
- 大学選びに迷われている方
進路相談やIB科目の学習サポートを受けたい方、IB生特有の悩みにIB経験者の教師とアドバイザーがフルサポートで寄り添います。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください!
▶ 無料相談はこちらから:お問い合わせ・無料相談